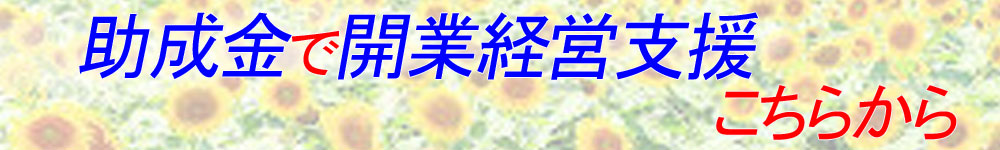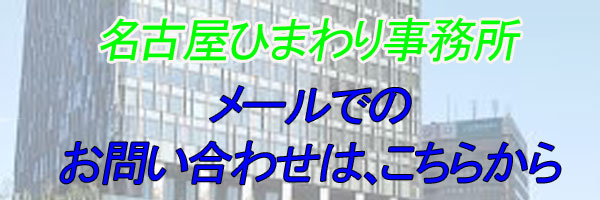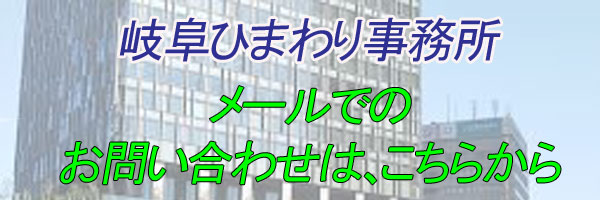愛知県で【助成金】で小規模多機能型居宅介護の開業・経営をご検討の方はこちらから
【介護事業 特化型事務所】 地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護 開業・経営支援
1.地域密着型サービスについて
地域密着型サービスとは、2005年に改正された介護保健法によって新規に設立された介護サービスのひとつです。
地域密着型介護サービスを利用できる対象者は、要介護認定で「要介護」以上に認定された人に限ります。
また、「要支援」に認定された方は、地域密着型介護予防サービスを受けることになり、その介護サービスは、地域密着型サービスの予防版ともいえます。
地域密着型サービスは、認知症(痴呆)や一人暮らしの高齢者などの増加を考え、要介護者たちが住み慣れた地域の近くで介護サービスが受けることが出来るようにと設立されました。
地域密着型サービスでは、地域の現在の状況にあわせて地域の特徴をいかしたサービスが、市町村が主体となって提供される介護サービスです。
2.地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護の概要
利用者の居宅で、または利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊したりして、提供される入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
小規模多機能型居宅介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
3.地域包括ケアシステムのなかで小規模多機能型居宅介護施設」の普及促進
地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域で人生の最期まで暮らし続けるよう高齢者を支援する制度で、介護保険の保険者である市町村を中心にケアマネジャーなどが連携して地域資源を生かしながら構築を図るものです。
政府は地域包括ケアシステムを強力に推進するため、「小規模多機能型居宅介護施設」の普及促進を打ち出しています。
上記にて説明しました通り、「小規模多機能型居宅介護施設」とは、高齢者の体調や希望に合わせて通所、宿泊、訪問などのサービスを組み合わせて、住み慣れた自宅で継続して生活できるよう支援する施設のことです。

「小規模多機能型居宅介護施設」は、自宅での生活を年中無休で支援する施設であり、地域密着型通所介護(小規模デイ)の機能も一部兼ねているため、小規模多機能型居宅介護施設を増やすほうが地域包括ケアシステムの構築が進むと見られています。
ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。
介護事業コンサルタント
愛知で介護事業コンサルティング
岐阜で介護事業コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
愛知で障害福祉サービス コンサルティング
岐阜で障害福祉サービス コンサルティング
助成金申請代行 独立開業経営支援
愛知で助成金申請代行
岐阜で助成金申請代行
給与計算代行 独立開業経営支援
愛知で給与計算代行
岐阜で給与計算代行
人事労務管理 独立開業経営支援
愛知で人事労務管理
岐阜で人事労務管理
会社設立
愛知で会社設立
岐阜で会社設立
派遣業 独立開業経営支援
愛知で派遣業 独立開業経営支援
岐阜で派遣業 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
愛知で建設業 独立開業経営支援
岐阜で建設業 独立開業経営支援
その他の許可申請
愛知でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
岐阜でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077